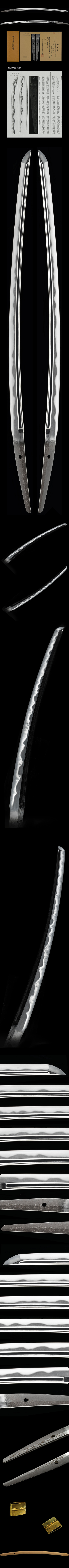紀充 刀 Kijyu Katana
No.200501筒井越中守藤原輝邦入道紀充 享保八年二月吉日 刀剣美術所載 身幅3.2cm匂深い濤瀾乱れ金筋砂流し頻りに掛る傑作 二尺三寸六分Tsutsui Ecchunokami Fujiwara Terukuni Nyudo Norimitsu, Auspicious day in February, 8th Kyoho, Published in the Token Bijutsu(Sword Art Collection), Mihaba 3.2cm, Deep Nioi, Toranmidare, Kinsuji and Sunagashi entered frequently, a masterpiece 71.6cm
- 銘表Mei-Omote
- 筒井越中守藤原輝邦入道紀充 筒井越中守藤原輝邦入道紀充 Tsutsui Ecchunokami Fujiwara Terukuni Nyudo Norimitsu
- 裏銘Ura-mei
- 享保八年二月吉日享保八年二月吉日 Auspicious day in February, 8th Kyoho
- 登録証Registration
- 栃木県 Tochigi 昭和26年3月30日 3/30/26(Showa)
- 時代Period
- 江戸中期享保八年Middle Edo period, 8th Kyouhou
- 法量Size
-
刃長 71.6cm (二尺三寸六分) 反り 1.8cm
元幅 3.2cm 先幅 2.2cm 元重 0.67cm 鎬厚 0.75cm 先重 0.55cm 鋒長 3.3cm 茎長 20.5cm 重量 654gHachou 71.6cm (二尺三寸六分) Sori 1.8cm
Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.67cm Shinogi-Thikess 0.75cm Saki-Kasane 0.55cm Kissaki-Chou 3.3cm Nakago-Chou 20.5cm Weight 654g - 国Country
- 越中Ecchu
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸厚くつき、地景よく入り、鉄冴える。Itamehada, Mixed Mokumehada, Jinie entered thick, Chikei entered frequently, Iron is clear.
- 刃文Hamon
- のたれに、大互の目・丁子乱れ交じり、足・葉入り、沸深くつき、金筋・砂流し幾重にも頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。Notare, Ohgunome, Mixed Choujimidare, There are Ashi and You, Nie entered deeply, Kinsuji and Sunagashi entered over and over, Nie deeply, Nioikuchi is bright and clear.
- 帽子Boushi
- 乱れ込んで、先掃き掛けて返る。Midarekonde, Sakihakikakete-Kaeru
- 茎Nakago
- 生ぶ、茎尻は入山形、鑢目筋違化粧、目釘孔一。Ubu, Nakagojiri is Iriyamagata, Yasurimesujikaikesyou, Mekugiana is one(1).
- ハバキHabaki
- 金着銅一重。Single Kinkisedou(Single layer of gold-plated copper.)
- 説明Drscription
- 筒井紀充(のりみつ)は、大和文殊派の鍛冶である越中守包国の子として寛文六年に生まれ、輝邦と銘し、宝永頃に入道して紀充と切る。初め大坂で鍛刀し、享保年中は河内、のちに大和郡山の九条に移る。戦国大名筒井順慶の一族と伝え、銘によく筒井の姓を切っている。作風は、大坂新刀の影響が強く、特に津田越前守助広に私淑しており、助広を想わせる沸・匂いの深い濤欄刃を焼き、大和文殊派の鍛冶であるので、地鉄の柾が強く、それが刃中に絡むと金筋・砂流しが長くよく働く。この刀は、地沸厚くつき、のたれに、互の目・丁子刃交じり、濤瀾乱れとなり、金筋・沸筋・砂流し頻りに掛かり、刃中よく働き、沸匂深く、匂口明るく冴える、助広に劣らぬ出来の傑作である。 Tsutsui Norimitsu was born in 6th Kanbun as the son of Ecchunokami Kanekuni, a blacksmith of the Yamato Monju school. He took the name Terukuni and became a monk around the Houei period, taking the name Norimitsu. Initially forged in Osaka, it was moved to Kawachi during the Kyoho era and later to Kujo in Yamatokooriyama. Said to be a descendant of the Sengoku Daimyo Tsutsui Junkei, the Tsutsui surname is often included in the inscription. His style is heavily influenced by Osaka Shinto. He particularly admires Tsuda Echizennokami Sukehiro, and forges Toran-ba with deep Nie and Nioi that evokes Sukehiro's work. As a Yamato Monju-style blacksmith, the Jigane has a strong Masa, when it is incorporated into the sword, Kinsuji and Sunagashi entered long and frequently. This sword has thick Jinie, Notare, Gunome and Mixed Choujiba, Toran-Midare, Kinsuji and Niesuji, Sunagashi entered frequently, IT works well in sword, Deep Nie-Nioi, Nioikuchi is bright and clear. a masterpiece that is not inferior to Sukehiro.