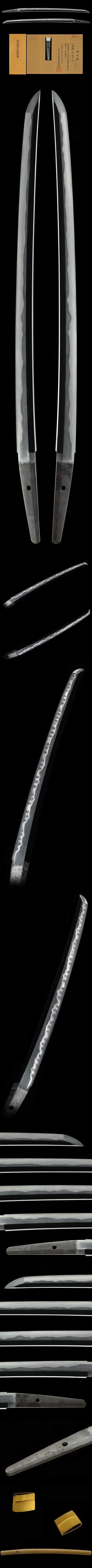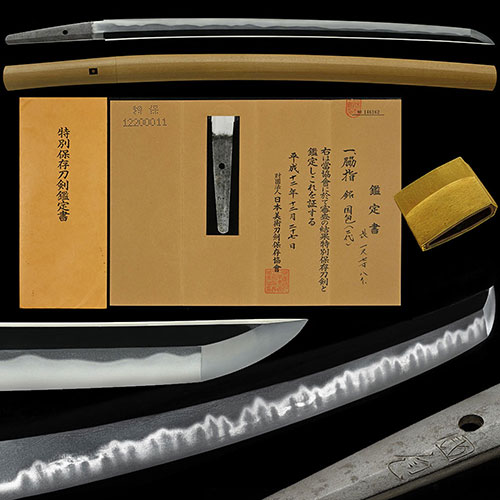
国包 二代 脇差Kunikane II Wakizashi
No.752957脇差 国包 二代 柾目肌に大小の沸が深く美しく輝き金筋砂流し頻りに掛る最高傑作 一尺七寸八分Wakizashi Kunikane II Masamehada with Big and small Nie shining beautiful, Kinsuji and Sunagashi-shikirinikakaru A masterpiece 54.0cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 国包国包 Kunikane
- 登録証Registration
- 三重県 Mie 平成1年6月20日 6/20/1(Heisei)
- 時代Period
- 江戸初期寛文頃Early Edo period around Kanbun period
- 法量Size
-
刃長 54.0cm (一尺七寸八分) 反り 0.8cm
元幅 3.0cm 先幅 2.0cm 元重 0.53cm 鎬厚 0.67cm 先重 0.45cm 鋒長 3.5cm 茎長 8.8cm 重量 475gHachou 54.0cm (一尺七寸八分) Sori 0.8cm
Moto-Haba 3.0cm Saki-Haba 2.0cm Moto-Kasane 0.53cm Shinogi-Thikess 0.67cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 3.5cm Nakago-Chou 8.8cm Weight 475g - 国Country
- 陸奥Mutsu
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反りやや浅く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Slightly shallow Sori, Chu-Kissaki.
- 鍛Kitae
- 柾目肌に、地沸厚くよくつき、地景よく入り、鉄冴える。Masamehada, Jinie entered thick and frequently, Chikei entered frequently, Iron is clear.
- 刃文Hamon
- 丁子乱れに、互の目交じり、足・葉よく入り、沸深くよくつき、粗沸を交え、金筋・砂流し頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。Choujimidare, Mixed Gunome, There are Ashi and You frequently, Deep Nie entered frequently, Mixed Rough-Nie(Ara-Nie), Kinsuji and Sunagashi-shikirinikakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.
- 帽子Boushi
- 直ぐに小丸。Suguni-Komaru
- 茎Nakago
- 生ぶ、先栗尻、鑢目筋違化粧、目釘孔一。Ubu, Sakikurijiri, Yasurimesujikai-Kesyou, Mekugiana is one(1)
- ハバキHabaki
- 金着二重。Double Kinkise(Double layered with gold.)
- 説明Drscription
- 初代国包は、大和保昌の末流と称し、名を本郷源蔵といい、文禄元年に仙台に生まれ、伊達政宗の命により京の越中守正俊門となり修行する。その後仙台に戻り、寛永三年には山城大掾を受領、大和保昌伝の作域を再現した。寛文四年に七十四歳で没。二代国包は、本郷吉右衛門といい、慶長十六年に初代国包の子として生まれ、正保二年に34歳で家督を相続、寛文七年山城守を受領。寛文十二年没(六十一歳)。以後国包家は明治維新まで仙台藩工として大いに繁栄した。本作は、二代国包の山城守受領前の作で、柾目肌に地沸が厚くつき黒く輝く美しい冴えた地鉄に、足が長く入る互の目丁子を華やかに焼き、銀砂を撒いたように大小の沸が深く美しく輝き、金筋砂流し頻りに掛り、匂深く匂口明るく冴える二代国包の最高傑作である。The first Kunikane was a descendant of Yamato Yasumasa and was named Hongo Genzo. He was born in Sendai in 1592(1st Bunroku) and, by order of Date Masamune, became a disciple of Ecchu no Kami Masatoshi in Kyoto. He returned to Sendai, and in 1626(3rd Kanei) he received the title of Yamashiro Daijo, recreating the style of Yamato Yasumasaden.
He died in the fourth year of Kanbun(1664)at the age of 74.
Kunikane II, called Hongo Kichiemon, was born in 1611(16th Keicho) as the son of the first Kunikane, inherited the family headship at the age of 34 in 1645, and received the title of Yamashironokami in 1667(7th Kanbun). He died in the 12th Kanbun(1672), From then on, the Kunikane family prospered greatly as craftsmen in the Sendai domain until the Meiji-Ishin(restoration).
This sword was made by the Kunikane II before he was appointed Yamashironokami, and has thick Jinie and Masamehada, Black Jigane shining beautiful and clear, There are long Ashi and Gunome-Chouji gorgeously, Big and Small-Nie entered deeply and shining beautifully, as if silver sand had been sprinkled on top, Kinsuji and Sunagashi-shikirinikakari, Deep Nioi and Nioikuchi is bright and clear, This is the second Kunikane's masterpiece.