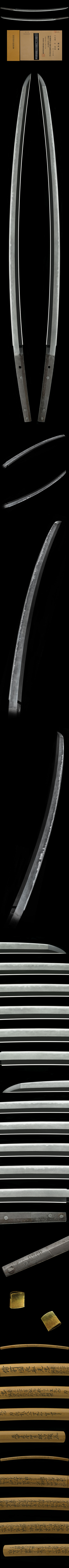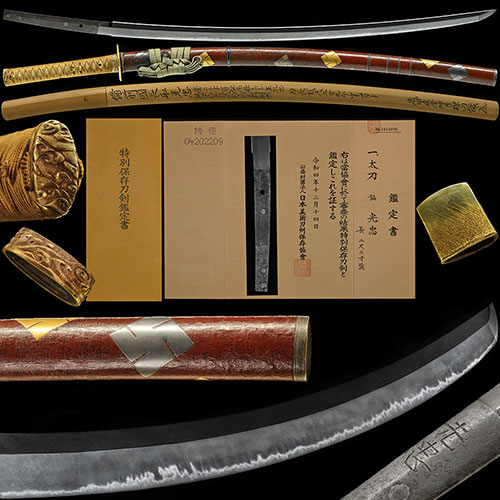
在銘太刀 光忠Zaimei Tachi Mitsutada
No.999434光忠 在銘太刀 長船祖 美しい地鉄に蛙子交える華やかな丁子乱れ傑作 卍紋散皮巻鞘打刀拵付 二尺二寸九分Mitsutada Zaimei Tachi Osafune, A masterpiece with beautiful Jigane, mixed Kawazuko and Gorgeouse Chouji-Midare, With Swastika pattern Monchirashi Kawamaki-saya Uchigatana-Koshirae, 69.5cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 光忠 光忠 Mitsutada
- 登録証Registration
- 大阪府 Osaka 昭和26年6月22日 6/22/26(Showa)
- 時代Period
- 鎌倉中期 建長頃Middle Kamakura period, Around Kencho era
- 法量Size
-
刃長 69.5cm (二尺二寸九分) 反り 2.0cm
元幅 2.67cm 先幅 1.76cm 元重 0.57cm 鎬厚 0.67cm 先重 0.43cm 鋒長 3.65cm 茎長 19.8cm 重量 667gHachou 69.5cm (二尺二寸九分) Sori 2.0cm
Moto-Haba 2.67cm Saki-Haba 1.76cm Moto-Kasane 0.57cm Shinogi-Thikess 0.67cm Saki-Kasane 0.43cm Kissaki-Chou 3.65cm Nakago-Chou 19.8cm Weight 667g - 国Country
- 備前Bizen
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反りやや深く、腰反りつき、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, Slightly deep Sori, Koshizori-tsuki, Chu-Kissaki.
- 鍛Kitae
- 板目肌つみ、杢目・小杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景細かくよく入り、乱れ映りたつ。Itamehada-tsumi, Mokume and Mixed Small-Mokumehada, Jinie entered fine and thick, Chikei entered frequently and finely, Midare-Utsuritatsu.
- 刃文Hamon
- 丁子乱れに、小丁子・蛙子風の丁子・互の目・飛び焼きなど交え、足・葉頻りに入り、匂出来、小沸付き、金筋頻りに掛かり、匂口明るい。Choushi-Midare, Small-Chouji, Kawazuko-style Chouji, Gunome, Mixed Tobiyaki, There are Ashi and You frequently, Nioi-Deki, Small-Nie-tsuki, Kinsuji entered frequently, Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 帽子、のたれ込んで小丸。Boushi Notarekonde-Komaru
- 茎Nakago
- 磨上、先切、鑢目浅い勝手下り、目釘孔四内三埋。Suriage, Sakikiri, Yasurime shallow Kattesagari, Mekugiana are three of the four are filled.
- ハバキHabaki
- 金着一重。Single Kinkise (Wearing a single layer of gold.)
- 拵Sword mounitings
- 革巻鞘卍紋散鞘打刀拵
法量
長100.0cm 反4.1cm
説明
鐔 銘 山城住 埋忠重吉 山銅地柳に鷺図金色絵。 縁頭 金着波濤図。 目貫 赤銅地獅子図金色絵。蜂須賀家の卍紋が入る優品。
革巻鞘卍紋散鞘打刀拵
法量
長100.0cm反4.1cm
説明
鐔 銘 山城住 埋忠重吉 山銅地柳に鷺図金色絵。 縁頭 金着波濤図。 目貫 赤銅地獅子図金色絵。蜂須賀家の卍紋が入る優品。 - 説明Drscription
- 光忠は、古備前近忠の子と伝え、長船派の祖であり、長光の父で、長船随一の名匠である。豪壮な体配と、重花丁子・蛙子丁子など変化に富んだ 華麗な作風を呈し、国宝3口・重要文化財13口・重要美術品12口が指定されており、幾多の名作を残している。織田信長は、光忠の華やかな作を特に好み、二十数振りを所持した。この刀は、板目肌に、杢目交じり、地沸微塵に厚く付き、地景よく入り、乱れ映りたつ柔らかみのある精良な地鉄に、銘振りからも初期作の古備前風から華やかな出来となる移行期の作ながら、蛙子風の丁子などを交える丁子乱れに小丁子を交えた華やかな作域を呈し、小沸厚くつき、強く輝く金筋が長く入り、刃中の働き盛んで、匂口明るい傑作である。在銘作が極めて稀な光忠において、本作の二字銘は鑽枕が立つ程鮮明に残り珍重である。付帯する蜂須賀家の卍紋が金銀高蒔絵で入る皮巻拵は、桃山時代はあると思われる。Mitsutada is said to be the son of Kobizen Chikatada, the founder of the Osafune school, the father of Nagamitsu, and the greatest master of Osafune. Magnificent sword and works are rich in variety and show a gorgeous style, such as Juka-Chouji and Kawazuko-Chouji. There are three Kokuho, 13 Juyo-Bunkazai, 12 Juyo-Bijutsuhin, and it leave many masterpieces.
Oda Nobunaga was particularly fond of Mitsutada's gorgeous works and owned over twenty of them.
This sword has Itamehada, Mixed Mokume, Jinie entered fine and thick, Chikei entered finely, Midare-Utsuritatsu with a soft and fine Jigane. The inscription indicates that this is a work from the transitional period from the early Ko-Bizen style to a more glamorous work, but it also displays a gorgeous area of workmanship with Small-Chouji, Kawazuko-style Chouji and Mixed Chouji-Midare. Small-Nie entered thickly, Kinsuji entered long and shining strong. active work in the sword and Nioikuchi is bright, A masterpiece. Among the extremely rare Mitsutada swords bearing signatures, the two-character signature on this sword remains so clear that it is marked with Tagane-Makura, making it highly prized. The Koshirae leather wrapping, which bears the Hachisuka family crest in gold and silver taka-maki-e, is thought to date to Momoyama period.