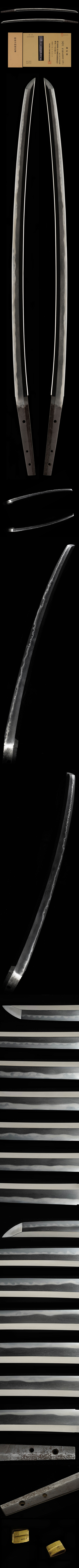備州長船秀助 在銘太刀 Bisyu Osafune Hidesuke Zaimei-Tachi
No.035787在銘太刀 備州長船秀助 時代半太刀拵入 南北朝後期 乱れ映り立つ名品 二尺二寸四分Zaimei-Tachi Bisyu Osafune Hidesuke in Jidai-HanTachi-Koshirae Late Nanbokucho MidareUtsuritatsu a masterpiece 67.8cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 備州長船秀助備州長船秀助 Bisyu Osafune Hidesuke
- 登録証Registration
- 大阪府 Osaka 昭和55年5月13日 5/13/55(Showa)
- 時代Period
- 南北朝時代Nanbokucho Era
- 法量Size
-
刃長 67.8cm (二尺二寸四分) 反り 1.7cm
元幅 2.8cm 先幅 1.9cm 元重 0.62cm 鎬厚 0.72cm 先重 0.45cm 鋒長 2.6cm 茎長 17.1cm 重量 610gHachou 67.8cm (二尺二寸四分) Sori 1.7cm
Moto-Haba 2.8cm Saki-Haba 1.9cm Moto-Kasane 0.62cm Shinogi-Thikess 0.72cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 2.6cm Nakago-Chou 17.1cm Weight 610g - 国Country
- 備州Bisyu
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反りやや深く、腰反りつき、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, Slightly deep Sori, Koshizori-tsuki, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 板目肌に、杢目交じり、所々大肌交え、乱れ映りたつ。Itamehada, Mixed Mokume, In some places Mixed Oh-hada, Midare-Utsuritatsu.
- 刃文Hamon
- 互の目に、のたれ刃・丁子刃交じり、湯走りかかり、足・葉入り、匂出来、小沸つき、金筋かかる。Gunome, Notare-ba, Mixed Choujiba, Yubashirikakari, There are Ashi and You, Nioideki, Small-nie-tsuki, Kinsuji-kakaru.
- 帽子Boushi
- のたれ込んで小丸、先掃きかける。Notarekonde-Komaru, Sakihakikakeru
- 茎Nakago
- 大磨上、先切、鑢目勝手下、目釘孔三。Ohsuriage, Sakikiri, Yasurimekattesagari, Mekugiana are three(3)
- ハバキHabaki
- 金色絵二重。Kiniroe double
- 拵Sword mounitings
- 金箔散八重牡丹塗鞘半太刀拵 [江戸時代]
法量
長さ97.9cm 反り4.8㎝
説明
鐔 素銅地葵形、 総金具 赤銅魚子地金覆輪。 目貫 赤銅地獅子図。 笄 赤銅魚子地雁図金色絵。Kinpaku Chirashi Yaebotan(Gold leaf scattered double peony) Nurisaya Handachi-Koshirae (Edo era)
Length: Suakaji Aoi-gata
Total metal fitting: Syakudounanakoji Kinfukurin
Menuki: Syakudouji Shishizu(Shakudo ground lion figure)
Kougai: Syakudounanakoji Karizu(wild goose) Kiniroe - 説明Drscription
- 秀助は、初代が南北朝前期康永頃、二代が南北朝後期から室町初期にかけて活躍している。小反りは、南北朝時代の長船正系以外の長船鍛冶を指し、主な刀工としては、秀光、政光 、師光などがいる。この太刀は、反りやや深く、腰反りつき、鋒小さめに結ぶ品の良い姿で、板目肌に杢目が交じり、乱れ映り立つ地鉄に、互の目に、のたれ・小互の目・丁子刃など交え、変化に富む刃を焼く名品である。相伝備前の特徴が表れ長義の系統かとも思われる。The first Shusuke was active around the Nanbokucho pre-Kouei period, and the second was active from the late Nanbokucho period to the early Muromachi period.Small-sori refers to Osafune blacksmiths other than Osafune's regular line during the Nanbokucho era, and the main swordsmiths include Hidemitsu, Masamitsu, and Moromitsu.
This Tachi has slightly deep Sori, Koshizoritsuki, A refined figure that ties Kissaki on a small scale, Itamehada and mixed Mokume, MidareUtsuritatsu Jigane, Gunome, Notare, Small-Gunome, Mixed Choujiba, It is a masterpiece that blades Yaki that are rich in variety.
The characteristic of SoudenBizen appears and it is thought that it is a lineage of Nagayoshi.