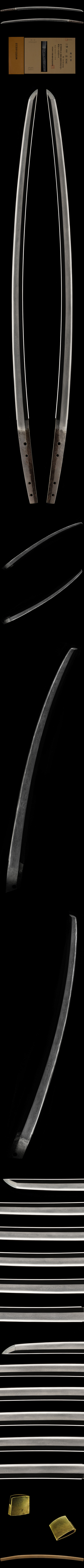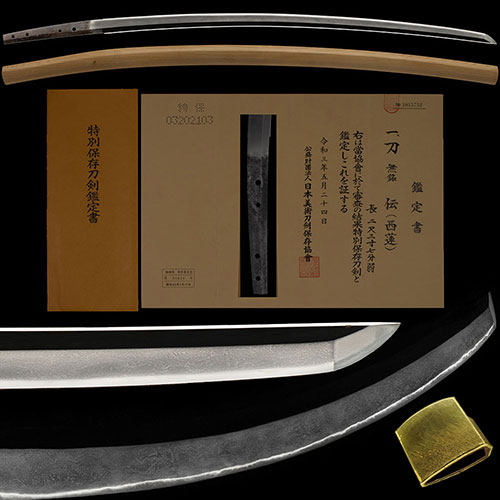
西蓮 刀Sairen Katana
No.100547刀 西蓮 大左祖父 鎌倉後期永仁頃 約730年前 小足頻りに入り匂口締りごころに明るい優品 二尺六寸七分Sairen Taisa Grandfather Ohsa around the late Kamakura era. Ounin about 730 years ago Small-Ashi entered well , Nioikuchi is bright in shimarigokoro a excellent sword 71.8cm
ご成約Sold
- 極めKiwame
- 西蓮Sairen
- 登録証Registration
- 福岡県 Fukuoka 昭和43年9月19日 9/19/43(Showa)
- 時代Period
- 鎌倉時代Kamakura era
- 法量Size
-
刃長 71.8cm (二尺六寸七分) 反り 1.9cm
元幅 2.7cm 先幅 1.7cm 元重 0.57cm 鎬厚 0.67cm 先重 0.43cm 鋒長 2.5cm 茎長 18.6cm 重量 663gHachou 71.8cm (二尺六寸七分) Sori 1.9cm
Moto-Haba 2.7cm Saki-Haba 1.7cm Moto-Kasane 0.57cm Shinogi-Thikess 0.67cm Saki-Kasane 0.43cm Kissaki-Chou 2.5cm Nakago-Chou 18.6cm Weight 663g - 国Country
- 筑前Chikuzen
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反り深く、腰反りつき、小鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, Deep Sori, Koshizori-tsuki, Small-Kissaki.
- 鍛Kitae
- 板目肌に、杢目肌交じり、大肌を交え、地沸微塵に厚くつき、肌立ち、地景よく入り、映りたつ。Itamehada, Mixed Mokume-hada, Mixed Oh-hada, Jinie entered finely and thick, Hadatachi, Chikei entered well. Utsuritatsu.
- 刃文Hamon
- 直刃調に、小互の目交じり、二十刃掛り、小足頻りに入り、小沸つき、匂口締まりごころに明るい。Suguha-style, Mixed Small-Gunome, Nijuba-kakari, Small-Ashi entered well, Small-Nie-tsuki, Nioikuchi shimkri-gokoro is bright.
- 帽子Boushi
- 直ぐに小丸Suguni-Komaru
- 茎Nakago
- 大磨上、先切、鑢目勝手下り、目釘孔四Ohsuriage, Sakikiri, Yasurime-kattesagari, Mekugiana are four(4)
- ハバキHabaki
- 金着一重Gold-clad single layer
- 説明Drscription
- 西蓮は、筑前鍛冶の祖と伝える良西の子、そして実阿の父、大左の祖父にあたる。鎌倉後期永仁頃の法師鍛冶で、名を国吉といい、西蓮は法師名である。「筑前国博多住談議所西蓮法師国吉」などの在銘作があり、鎌倉幕府が、文永・弘安の役(いわゆる元寇)後の弘安9年に博多に設置した鎮西談議所に属し、蒙古の襲来に備え鍛刀している。この刀は、元は80cm程の太刀で、反り深く、腰反りつき、小鋒に結ぶ優美な姿で、映りの立つ黒みをおびた杢目肌に、地景よく入り、直刃調に、小互の目交じり、二十刃掛り、小足頻りに入り、小沸よくつき、匂口締りごころに明るい優品である。Sairen is the son of Ryosai, who is said to be the founder of Chikuzen blacksmithing, Jitsua's father, and Osa's grandfather. A master blacksmith from the late Kamakura era Eihito, whose name is Kuniyoshi, and Sairen is his master's name. There are inscriptions such as ``Chikuzen Province Hakata Judangisho Sairenboshi Kuniyoshi,'' and the Chinzei Dangisho was established in Hakata by the Kamakura Shogunate in the 9th year of Koan after the Bunei-Koan War (so-called Genko). It belongs to the , and is forged in preparation for the Mongol invasion.
This sword was originally a sword about 80cm long.Deep Sori, Koshizori-tsuki, Small-Kissaki graceful figure, Utsuritatsu with dark Mokumehada, Chikei entered well, Suguha-style,Mixed Small-Gunome, Nijuba-kakari, Small-Ashi entered well, Small-Nie-tsuki, Nioiguchi-shimarigokoro a bright and excellent sword.