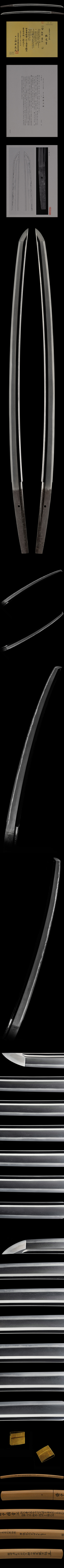青江 刀 重要刀剣Aoe Katana Juyo-token
No.118913第63回重要刀剣 青江 特別重要候補 乱れ映り立ち金筋掛る格調高い名刀 二尺二寸九分半63th Juyo-Token Aoe Tokubetsu Juyo candidate Midare-Utsuri, Kinsuji-kakaru, magnificent sword 69.5cm
ご成約Sold
- 極めKiwame
- 青江Aoe
- 時代Period
- 鎌倉時代Kamakura period
- 法量Size
-
刃長 69.5cm (二尺二寸九分半) 反り 1.6cm
元幅 3.1cm 先幅 2.2cm 元重 0.64cm 鎬厚 0.68cm 先重 0.55cm 鋒長 3.8cm 茎長 19.7cm 重量 690gHachou 69.5cm (二尺二寸九分半) Sori 1.6cm
Moto-Haba 3.1cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.64cm Shinogi-Thikess 0.68cm Saki-Kasane 0.55cm Kissaki-Chou 3.8cm Nakago-Chou 19.7cm Weight 690g - 国Country
- 備中Bichu
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反りやや深く、腰反り付き、中鋒。Shinogi-dukuri,Iorimune,Widely Mihaba,Deep sori, with Koshizori, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸微塵に厚く付き、地景入り、淡く映りたつ。Itame-hada,mixed Mokume-hada, Jinie is finely thick,Chikei comes out faintly and shines.
- 刃文Hamon
- 直刃調に、互の目交じり、湯走り・二十刃掛り、足・葉よく入り、小沸よくつき、所々粗めの沸が付き、金筋・沸筋掛り、匂口明るく冴える。Suguha style, mixed Gunome,Yubashiri,Nijuuba-kakari, there are many Ashi and You,Konie often entered, there is rather coarse Nie here and there, Kinsuji, Nioikuchi is bright and clear.
- 帽子Boushi
- 僅かに乱れ込んで小丸。Slightly Midarekomi Komaru
- 茎Nakago
- 大磨上、先切、鑢目切、目釘孔一。Ohsuriage,Sakikiri, Yasurimekiri, Mekugi is one(1)
- ハバキHabaki
- 金着二重。Double layered gold (Kinkise nijū.)
- 拵Sword mounitings
- 桐勝虫図金蒔絵鞘打刀拵[江戸時代]
法量
長さ99.5cm 反り3.6㎝
説明
鍔 銘 横谷宗知 四分一地波千鳥図。 縁頭鐺 銘 義行造 赤銅磨地窓花図金色絵。 目貫 牡丹図金銀色絵。 勝虫を金蒔絵、桐紋を影蒔絵とし地に金梨子地を施している。Kirikachimushi-zu Kinmakie Sayauchikatana-Koshirae (Edo period)
Size
Length: 99.5cm
Sori:3.6cm
Description
Tsuba: Mei Yokoya Munetoshi(横谷宗知) Shibuichi Jinami Chidori-zu
Fuchigashira Kojiri:Mei Yoshiyuki-dukuri Syakudou Migakiji Madohana-zu Kiniroe
Megashira:Botanzu Kingin Iroe. Kinmakie is Katchimushi , Kirimon is Kagemakie and Kinnashiji is applied to the ground. - 説明Drscription
- 備中青江派は、備中高梁川下流域を中心に活躍した刀工群で、平安末期の守次を祖として始まると伝えられ、平安末期から鎌倉前期暦仁頃までのものを古青江、それ以降を青江と大別している。この刀は、身幅広く、中鋒僅かに延びごころとなる鎌倉末期の姿で、板目肌に杢目交じり、地景よく入り、乱れ映り立つ明るく美しい地鉄に、直刃調に、小互の目・小丁子交じり、湯走り・二十刃・飛び焼き掛り、足・葉よく入り、小沸付き、金筋・沸筋掛るなど変化に富み、匂口明るく冴える。頗る健全で、見所が多く、格調高い名刀である。Bichu-Aoe faction school is a group of swordsmiths who were active mainly in the lower reaches of the Bichu-Takahashi River. It is roughly divided into.
This sword has a wide Mihaba and Chu-Kissaki is slight Nobigokoro sword looks like the end of Kamakura.
This sword has wide body, Itmaehada with Mokume-hada,with finely thick with Chikei,the bright Jigane with MIdareutsuri, Suguhacho, small Gunome, small Chojimajiri, Yubashiri, Nijuba ,Tobiyakikakari,There are many Ashi and Ha. with Konie, Kinsuji, Niesujikakari, It is rich for a change.It is clear brightly.It is a very good condition, well-known sword with many highlights.