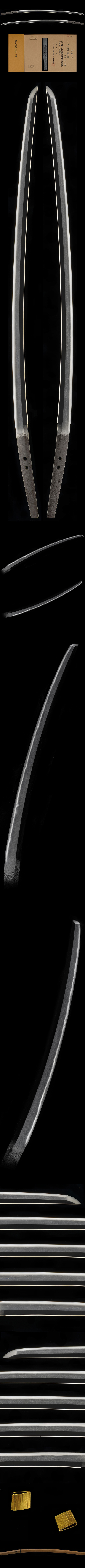尻懸 刀 Shikkake Katana
No.130345刀 尻懸 鎌倉後期 映り立ち小互の目に沸筋頻りに掛る匂口明るい優品 二尺二寸八分Katana Shikkake Late Kamakura period Utsuritachi Small-Gunome Niesuji-shikirinikakaru Nioikuchi is bright A masterpiece 69.2cm
ご成約Sold
- 極めKiwame
- 尻懸Shikkake
- 登録証Registration
- 埼玉県 Saitama 昭和48年5月25日 5/25/48(Showa)
- 時代Period
- 鎌倉後期Late Kamakura period
- 法量Size
-
刃長 69.2cm (二尺二寸八分) 反り 1.5cm
元幅 2.8cm 先幅 1.7cm 元重 0.56cm 鎬厚 0.67cm 先重 0.46cm 鋒長 2.7cm 茎長 19.4cm 重量 585gHachou 69.2cm (二尺二寸八分) Sori 1.5cm
Moto-Haba 2.8cm Saki-Haba 1.7cm Moto-Kasane 0.56cm Shinogi-Thikess 0.67cm Saki-Kasane 0.46cm Kissaki-Chou 2.7cm Nakago-Chou 19.4cm Weight 585g - 国Country
- 大和Yamato
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反りやや深く、腰反り付き、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, slightly deep Sori, Koshizoritsuki, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 板目肌つみ、杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景入り、映りたつ。Itamehada-tsumi, Mixed Mokume-hada, Jinie entered fine and thick, Chikei entered, Utsuri-tatsu.
- 刃文Hamon
- 直刃調に、小互の目交じり、湯走り掛り、足・葉頻りに入り、島掛り、小沸深くよくつき、沸筋頻りに掛り、砂流し掛り、匂口明るい。Suguba-style, Mixed Small-Gunome, Yubashiri-kakari, There are many Ashi and You,Shimagakari, Small- Nie entered well,Niesuji shikirini-kakari, Sunagashi-kakari,Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 直ぐに小丸、先掃きかける。Sugunikomaru, Sakihakikakeru
- 茎Nakago
- 大磨上、先浅い栗尻、鑢目浅い勝手下り、目釘孔二。Oh-suriage, Shallow-Kurijiri tip, Yasurime-shallow-kattesagari, Mekugiana are two(2)
- ハバキHabaki
- 金着一重Gold-clad single layer
- 説明Drscription
- 大和尻懸派は、鎌倉後期正応(1288年)頃の則長を祖とし、手搔派と同じく東大寺に隷属していた刀工群で、南北朝時代にかけて繁栄している。この刀は、先幅細くなり、腰反り付き、中鋒となる鎌倉後期の姿で、板目肌に、杢目交じり、地沸微塵に厚くつき、映りたち、地景入る総体に詰んだ地鉄に、直刃調に、小互の目交じり、地沸深くつき、沸筋砂流し頻りに掛るなど刃中見事に働き、匂口明るい優品である。The Yamato Shirigake school, whose founder was Norinaga in the late Kamakura period (1288), was a group of swordsmiths who, like the Tegai school, were subordinated to Todaiji Temple, and prospered until the Nanbokucho era.
This sword has a tapered Sakihaba, Koshizoritsuki, In the form of late Kamakura period that became Chu-Kissaki. Itamehada, Mixed Mokume, Jinie entered fine and thick, Utsuritachi, Chikei entered all tsunda-Jigane, Suguha-style, mixed Small-Gunome, Jinie entered deeply, Niesuji and Sunagashi-shikirinikakaru, It works good in sword, Nioikuchi is bright, A masterpiece.