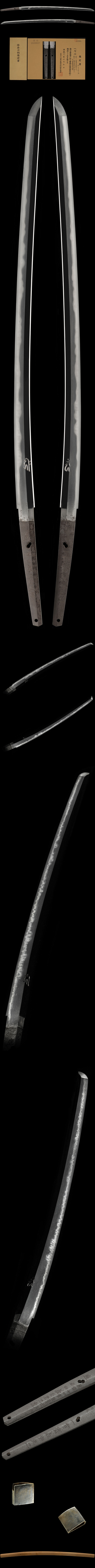義弘 刀Yoshihiro Katana
No.179175刀 郷写し 一貫斎義弘作之 天保十四癸卯年正月日 松皮風の地鉄に金筋幾重にも長く頻りに掛る傑作 ニ尺四寸一分Katana Gou-Utsushi(copy) by Ikkansai Yoshihiro Korewo-Tsukuru New Year's Day in the 14th year of the Tempo U-doshi, Matsukaze-style Jigane, LongKinsuji hangs over and over A masterpiece 73.0cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 北辰 一貫斎義弘作之 北辰 一貫斎義弘作之 Hokushin Ikkansai Yoshihiro Korewo Tsukuru
- 裏銘Ura-mei
- 奉守 天保十四癸卯年正月日 応正田義臣君之需奉守 天保十四癸卯年正月日 応正田義臣君之需 House Tenpou 14 Mizunochi-U net Syogatsubi Soda Yoshiomi Kun no jyu ni Oujiru
- 登録証Registration
- 千葉県 Chiba 昭和53年9月22日 9/22/53(Showa)
- 時代Period
- 南北朝時代Nanbokucho Era
- 法量Size
-
刃長 73.0cm (ニ尺四寸一分) 反り 1.2cm
元幅 3.2cm 先幅 2.2cm 元重 0.70cm 鎬厚 0.79cm 先重 0.60cm 鋒長 3.8cm 茎長 21.1cm 重量 883gHachou 73.0cm (ニ尺四寸一分) Sori 1.2cm
Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.70cm Shinogi-Thikess 0.79cm Saki-Kasane 0.60cm Kissaki-Chou 3.8cm Nakago-Chou 21.1cm Weight 883g - 国Country
- 武蔵Musashi
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、重ね厚く、先幅広く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba
- 鍛Kitae
- 板目肌つみ、杢目・流れ肌交り、地沸微塵に厚くつき、地景太く頻りに入る。Itamehada-tsumi, Mokume, mixed Nagare-hada, Jinie entered fine and thick, Thick Chikei entered frequent.
- 刃文Hamon
- 互の目に、丁子刃交じり、湯走り・飛び焼き頻りに掛かり、足・葉頻りに入り、沸深くよくつき、荒めの沸を交え、金筋幾重にも頻りに掛り、砂流し頻りに掛かり、匂深く、匂口明るい。Gunome, Mixed Choujiba, Yubashiri, Tobiyaki-shikirini-kakari, There are many Ashi, Deep Nie entered, Mixed Rough Nie, Kinsuji hangs over and over, Sunagashi-shikirini-kakari, Deep Nie, Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 帽子、直ぐに小丸、先掃きかける。Boushi, Suguni-Komaru, Sakihaki-kakeru
- 茎Nakago
- 生ぶ、先栗尻、鑢目切、目釘孔二。Ubu, Sakikurijiri, Yasurimegiri, Mekugiana are two(2)
- ハバキHabaki
- 銀着一重。Silver-clad single layer
- 彫物Carving
- 表裏に梵字を彫る。Engrave Sanskrit characters on the front and back.
- 説明Drscription
- 一貫斎義弘は、名を鈴木蔵人といい、寛政九年駿河に生まれ、その銘が示すように、郷義弘に私淑して所謂まぜ鉄の肌物鍛を創出した。初め伊豆代官江川太郎左衛門に仕え、後に水戸で則重の末孫四代則利に則重伝の鍛法を学んだ。天保五年頃、前橋藩松平家に抱えられ、以後は前橋と江戸を行き来して鍛刀している。慶応元年64歳没。この刀は、3.2cmと身幅広く、重ね厚く、先幅広い豪壮な姿で、板目肌に流れごころ交じり、地沸が厚く付き、地景が太く頻りに入る松皮風の地鉄に、湯走り・飛び焼き頻りに掛かり、足・葉頻りに入り、金筋幾重にも長く頻りにかかるなど刃中見事に働き、匂沸深く、郷写し注文打ちの傑作である。北辰奉守の銘が入り、北辰信仰と或いは千葉周作道場との関係が窺われる。Yoshihiro Ikkansai, whose name was Kurando Suzuki, was born in Suruga in the 9th year of the Kansei era, and as his name suggests, he created the so-called Hadamono-Kitae of Maze-tetsu in favor of Go Yoshihiro.At first, he served Izu governor Tarozaemon Egawa, and later in Mito, he learned the martial arts of Norishige from Noritoshi, the fourth descendant of Norishige.Around the 5th year of Tenpō, he was taken in by the Matsudaira family of the Maebashi clan, and since then he has been making swords by going back and forth between Maebashi and Edo. He died at the age of 64 in the first year of Keio.
This sword has a wide Mihaba 3.2cm, Thick Kasane, Wide Sakihaba and majestic figure, Mixed Itame-hada-Nagaregokoro, Jinie entered thick, Matsukaze-style Jigane with thick Chikei, Yubashiri, Tobiyaki-shikirini-kakari, There are many Ashi and You, Kinsuji it works wonderfully in the blade, such as repeatedly hanging over and over. Deep Nioi, It is a masterpiece of custom-made Go copying. There is an inscription of Hokushin Hoshu, suggesting a relationship between the Hokushin faith and Chiba Shusaku Dojo.