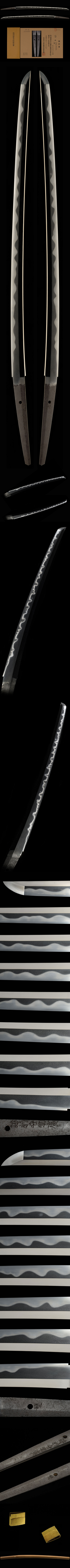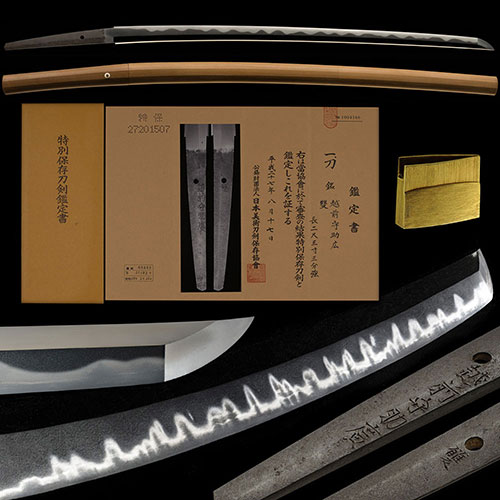
助広 刀Sukehiro Katana
No.181045越前守助広 雙 沸匂深い濤瀾乱れ傑作 新刀最上作 重要候補 二尺三寸三分Echizennokami Sukehiro Sou Deep NieNioi Douran-midare a masterpiece Shinto-Saijo-saku Juyo candidate 70.7cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 越前守助広 越前守助広 Echizennokami Sukehiro
- 裏銘Ura-mei
- 雙 雙
- 登録証Registration
- 福岡県 Fukuoka 昭和29年2月25日 2/25/29(Showa)
- 時代Period
- 江戸時代前期Early Edo period
- 法量Size
-
刃長 70.7cm (二尺三寸三分) 反り 1.0cm
元幅 3.3cm 先幅 2.1cm 元重 0.73cm 鎬厚 0.75cm 先重 0.53cm 鋒長 3.3cm 茎長 20.7cm 重量 741gHachou 70.7cm (二尺三寸三分) Sori 1.0cm
Moto-Haba 3.3cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.73cm Shinogi-Thikess 0.75cm Saki-Kasane 0.53cm Kissaki-Chou 3.3cm Nakago-Chou 20.7cm Weight 741g - 国Country
- 越前Echizen
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り浅く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Shallow Sori, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 小板目肌に、杢目・流れ肌交じり、地沸微塵につき、鉄明るく冴える。Small-Itamehada, Mokume, Mixed Nagarehada, Jinie entered finely. Iron is bright and clear.
- 刃文Hamon
- 焼き幅広く、互の目乱れに、丁子刃交じり、足・葉太く入り、沸深くよくつき、沸筋・砂流しかかり、匂深く、匂口明るく冴える。Wide Sakihaba, Gunome-Midare, Mixed Choujiba, There are thick Ashi and You, Deep Nie entered well, Niesuji and Sungashi-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.
- 帽子Boushi
- のたれて先尖りごころに深く返るNotarete-Sakitogarigokoro,Deep return
- 茎Nakago
- 産ぶ、先入山形、鑢目筋違、目釘孔一Ubu, Sakiiriyamagata, Yasurimesujikai, Mekugiana is one(1)
- ハバキHabaki
- 上質金着二重high-quality gold-clad double
- 説明Drscription
- 津田越前守助廣は、長曽弥虎徹、井上真改と並び称される新刀を代表する名工で、最上作に名を連ねており、殊に刃の明るさは新刀屈指といわれている。二代助広は、通称を甚之丞、寛永十四年(1637年)に摂州打出村(現兵庫県芦屋市)で生まれ、初代助廣門に入り、後に養子となっている。明暦三年(1657年)に越前守を受領、寛文七年(1667年)より大坂城代青山因幡守宗俊に召し抱えられ、天和二年(1682年)に四十六歳で没している。作風は、初めは石堂風の丁子刃であるが、次いで互の目から、大互の目となり、遂には濤瀾刃へと進歩を遂げる。雙と添銘を切るのは、父そほろ助広が没した後、寛文四年から六年に限られる。この刀は、身幅広く3.3cmあり、反りが浅く元先の幅差つく寛文新刀の姿で、助広三十歳頃の作となる。地沸微塵につく明るく冴えた地鉄に、鎬まで迫る焼き幅大きな互の目に、丁子を交じえ、玉焼きかかり、濤瀾乱れとなり、華やかに乱れ、足・葉太く入り、沸匂深く、沸筋・砂流し頻りにかかり、地刃共に明るく冴えて見事である。TsudaEchizennokami Sukehiro is a master craftsman who represents the new swords along with Yakotetsu Nagaso and Shinkai Inoue. The second Sukehiro, commonly known as Jinnojo, was born in 1637 in Uchide-mura, Setshu (now Ashiya City, Hyogo Prefecture), became the first Sukehiro, and was later adopted. In the 3rd year of Meireki (1657), he received the position of Echizen no kami, and in 1667, he was employed by Aoyama Inaba no Kami Munetoshi, the lord of the Osaka Castle, and died in the 2nd year of Tenwa (1682) at the age of 46. ing. At first, the style was Ishido-style clove blade, but then it changed from Gonomome to Ogonomome, and finally progressed to Toranba.
"Sou" is attached after his father Sohoro Sukehiro passed away.
limited to the 4th to 6th years of the Kanbun period.
This sword has a with of 3.3cm Mihaba, Shallow Sori Motohaba and wide difference int he width of the tip, and is made by Sukehiro around the age of 30.
Jinie entered finely and Jigane is clear and bright. Big Gunome enough to approach Shinogi, Mixed Chouji, Tamayaki-kakari, Douran-midare, Gorgeous Midare, There are thick Ashi and You, Deep NieNioi, Niesuji and Sunagashi-shikirini-kakari, Jiba is bright and clear a masterpiece.