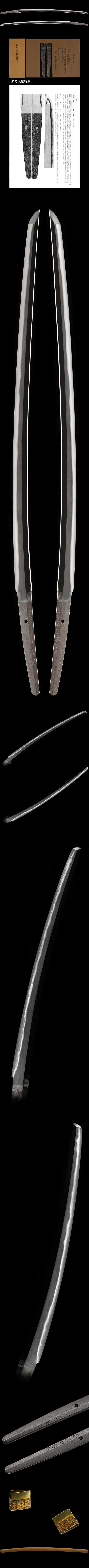一平安代 刀Ichinohira Yasuyo Katana
No.453578刀 一平安代 新刀大鑑所載 重要候補 沸美しくつき地刃明るく冴える傑作 ニ尺四寸九分Katana Ichinohira Yasuyo Listed Shinto-Taikan Juyo Candidate Beautiful Nie-tsuki Jiba is bright and clear 75.5cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 一平安代一平安代 Ichinohira Yasuyo
- 裏銘Ura-mei
- 薩州給黎郡住薩州給黎郡住 Sassyu Kiireigun Ryu
- 登録証Registration
- 佐賀県 Saga 昭和39年2月5日 2/5/39(Showa)
- 時代Period
- 江戸時代中期Middle Edo period
- 法量Size
-
刃長 75.5cm (ニ尺四寸九分) 反り 1.5cm
元幅 3.3cm 先幅 2.0cm 元重 0.69cm 鎬厚 0.79cm 先重 0.56cm 鋒長 3.1cm 茎長 20.7cm 重量 923gHachou 75.5cm (ニ尺四寸九分) Sori 1.5cm
Moto-Haba 3.3cm Saki-Haba 2.0cm Moto-Kasane 0.69cm Shinogi-Thikess 0.79cm Saki-Kasane 0.56cm Kissaki-Chou 3.1cm Nakago-Chou 20.7cm Weight 923g - 国Country
- 薩摩Satsuma
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り尋常、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Standard Sori, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 小板目肌流れごころにつみ、地沸厚くつき、地景細かく頻りに入り、鉄冴える。Small-Itamehada Nagaregokoro-tsumi, Jinie entered thick, Chikei entered finely frequent. Iron is clear.
- 刃文Hamon
- のたれて、互の目交じり、足・葉頻りに入り、沸深くよくつき、荒沸を交え、砂流しかかり、匂深く、匂口明るい。Notarete, Mixed Gunome, There are many Ashi and You, Nie entered deep and well, Mixed Ara-Nie, Sunagashi-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 直に小丸。Suguni-Komaru
- 茎Nakago
- 大磨上、先切、鑢目筋違、目釘孔二。Ohsuriage, Sakikiri, Yasurimesujikai, Mekugiana are two(2)
- ハバキHabaki
- 上質金着二重。High-quality gold-plated double layer
- 説明Drscription
- 一平安代は、通称を玉置小市といい波平一平安貞の長男として延宝八年(1680年)薩摩に生まれ、初めは父に鍛刀を習い、後に波平本家の大和守安行に学んだといわれている。享保六年(1721年)安代四十二歳の時に、同国の宮原正清と共に八代将軍徳川吉宗に召し出され江戸浜御殿で鍛刀し、安代と正清の二工はその技を認められ一葉葵紋を切ることを許され、その帰途の七月に主馬首を受領している。享保十三年に四十九歳で没。安代の作は吉宗に好まれたらしく、差料として用いられており、また重要文化財にも指定されている。
この刀は、磨上げた時に切ったと思われる切付銘が入り、受領銘があるところから、享保六年以降の作で、鎬厚く、身幅3.25cm、重量も900gを超える豪壮刀で、小板目肌良く詰み、流れ肌交じり、地沸厚くつき、地景が細かく入る精良で冴えた地鉄に、のたれて、互の目に交じり、足・葉頻りに入り、沸深くよくつき、大小の沸が美しく輝き、砂流しかり、匂深く、匂口明るく冴える傑作である。Ichinohira Yasuyo, commonly known as Tamaki Koichi, was born in Satsuma in 1680 as the eldest son of Namihei Ichinohira Yasusada, and first learned sword forging from his father, and later learned from Yamato no kami Yasuyuki, the main family of Namihira. It is said that.
In 1721, when Yasushiro was 42 years old, he and his fellow countryman Masakiyo Miyahara were summoned by the 8th Shogun Tokugawa Yoshimune to forge swords at Edohama Palace, and Yasushiro and Masakiyo were recognized for their skills and became Hitoyo. He was allowed to cut the hollyhock pattern (Ichiyou Aoimon), and received the Syumenokami in July on his way back.
He died in the 13th year of Kyoho at the age of 49. Yasushiro's work seems to have been favored by Yoshimune, and is used as a gift, and is also designated as Juyo Bunkazai.
This sword has an inscription on it that is thought to have been cut during suriage. Judging from the receipt Juryo-Mei, It was made after Kyoho 6th year. This sword has thick Shinogi, Mihaba3.25cm, and weighs more than 900g, Small-Itamehada-tsumi, Mixed Nagarehada, Jinie entered thick, Chikei entered sincerly clear good Jigane, Notarete, Mixed Gunome, There are many Ashi and You, Deep Nie entered well, Beautiful Nie shinning of all size,Sunagashi-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear A masterpiece.