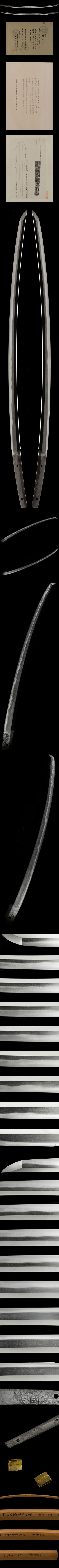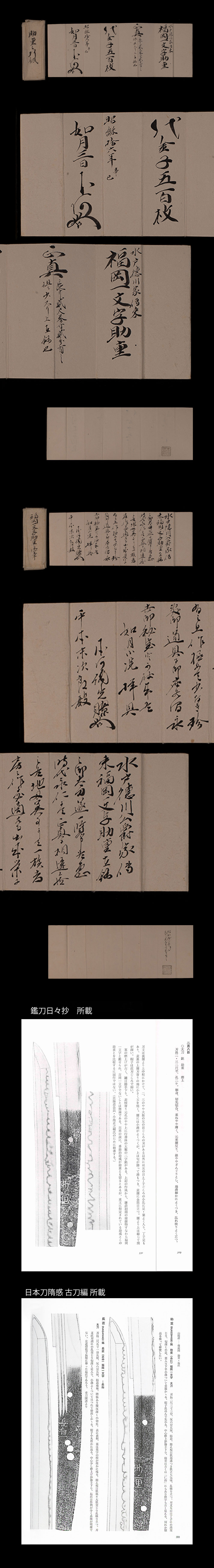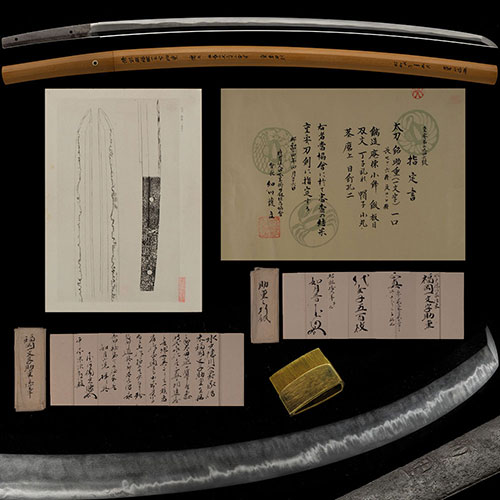
福岡一文字 助重 太刀Fukuoka Ichimonji Sukeshige Tachi
No.472275太刀 福岡一文字在銘 助重 水戸徳川家伝来 乱れ映り鮮やかに立ち丁子乱れ金筋頻りに掛る名品 二尺三寸二分五厘Juyo Token Fukuoka Ichimonji Inscription Mito Tokugawa Family Midareutsuri-tachi Vividly Choujimidare Kinsuji A masterpiece that hangs frequently 70.6cm
ご成約Sold
関連商品
- 銘表Mei-Omote
- 助重助重 Sukeshige
- 登録証Registration
- 三重県 Mie 昭和27年5月1日 5/1/27(Showa)
- 法量Size
-
刃長 70.6cm (二尺三寸二分五厘) 反り 2.0cm
元幅 2.7cm 先幅 1.7cm 元重 0.60cm 鎬厚 0.70cm 先重 0.45cm 鋒長 3.1cm 茎長 17.3cm 重量 638gHachou 70.6cm (二尺三寸二分五厘) Sori 2.0cm
Moto-Haba 2.7cm Saki-Haba 1.7cm Moto-Kasane 0.60cm Shinogi-Thikess 0.70cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 3.1cm Nakago-Chou 17.3cm Weight 638g - 国Country
- 備前Bizen
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反り深くつき、腰反り付き、小鋒。Shinogidukuri, Iorimune, standard Mihaba , Deep Sori, Small Kissaki
- 鍛Kitae
- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景よく入り、乱れ映り鮮やかに立つ。Itamehada, mixed Mokumehada, Jinie fine and thick, There are many Chikei, Midareutsuri-tatsu vividly.
- 刃文Hamon
- のたれて、互の目に、丁子・蛙子調の丁子など交じり、足・葉頻りに入り、小沸深くよく付き、元はよく沸えて金筋頻りに掛り、匂口明るい。Notarete, Gunome, Chouji , Kawazuko style mixed chouji, There are Ashi and You, Deep Konie well attached, Moto well Nie, Kinsuji, Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 乱れ込んで火炎風に先掃きかけて返る。Midarekonde Kaen style Sakihakikakete kaeru.
- 茎Nakago
- 磨上、先切、鑢目勝手下り、目釘孔二。Suriage, Sakikiri, Yasurimekattekudari, Mekugiana are 2.
- ハバキHabaki
- 上貝金無垢下貝金着二重。Uwagai gold solid lower, Shitagai gold wearing double.
- 説明Drscription
- 福岡一文字派は鎌倉初期、後鳥羽院御番鍛冶則宗を祖として始まると伝え、鎌倉中期にかけて多くの良工が輩出した。この派が一文字と呼称される所以は、茎に「一」の字をきることに因るが、銘は「一」の字のみのものと、他に「一」の字の下にさらに個銘を加えるもの、また個銘だけのものもある。これらの中で最も華やかで変化に富んだ丁子乱れの作風を展開しているのは、鎌倉中期の作である。助重は、古くは後鳥羽院御番鍛冶の助成同人という。この刀は、反り深く、腰反りつき、小鋒となる優美な姿で、乱れ映りが鮮やかに立ち、地沸が微塵につく精良な地鉄に、丁子乱れに、互の目・蛙子調の丁子など交え、足・葉頻りに入り、小沸深くつき、下半は更に良く沸えて、金筋頻りに掛り、匂口明るく健全である。The Fukuoka Ichimonji faction reported that it started with Gotobain Gobankaji Norimune in the early Kamakura period, and many good craftsmen were produced in the middle of Kamakura. The reason why this group is called Ichimonji is that the letter "IChi" is cut on the stem, but the inscription is only the letter "Ichi" and the other ones under the letter "Ichi". There are some that add inscriptions and some that only have individual inscriptions. Among these, Choujimidare's style, which is the most gorgeous and varied, is the work of the middle Kamakura period. Sukeshige used to be called Sukenari Doujin of Gotobain Gobankaji.
This sword is a graceful figure that becomes Deep Sori, Koshizoritsuki, Small Kissaki, Midare-utsuri stands vividly, Jinie fine and thick with fine Jigane , Choujimidare, Gunome, Kawazukochouji, etc., There are many Ashi and You, Konie deeply, the lower half is even better Niete, Kinsuji frequently hangs, Nioikuchi is bright Kenzen.