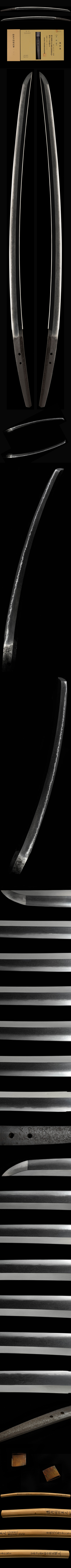兼元 刀 Kanemoto Katana
No.628239刀 兼元 孫六天文頃 田野辺先生鞘書 金筋砂流し掛る名品 時代印籠刻打刀拵付 二尺四寸一分Katana Kanemoto Magoroku Tenmon era profeccer Tanobe scabbard Kinsuji and Sunagashi-kakaru a masterpiece With Jidai Inrou Kizami-Uchigatana-Koshirae 70.1cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 兼元兼元 Kanemoto
- 登録証Registration
- 東京都 Tokyo 昭和26年3月31日 3/31/26(Showa)
- 時代Period
- 室町中期 天文頃 Middle Muromachi Tenmon era
- 法量Size
-
刃長 70.1cm (二尺四寸一分) 反り 1.8cm
元幅 3.1cm 先幅 2.1cm 元重 0.59cm 鎬厚 0.77cm 先重 0.45cm 鋒長 3.8cm 茎長 21.3cm 重量 807gHachou 70.1cm (二尺四寸一分) Sori 1.8cm
Moto-Haba 3.1cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.59cm Shinogi-Thikess 0.77cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 3.8cm Nakago-Chou 21.3cm Weight 807g - 国Country
- 美濃Mino
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反やや深く、中鋒やや延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Slightly deep Sori, Chu-Kissaki slightly extended
- 鍛Kitae
- 板目肌やや肌立ち、杢目交じり、地沸厚くつき、地景入り、映りたつ。Itamehada-hadatachi, Mixed Mokume, Jinie entered thickly, Chikei entered, Utsuritatsu
- 刃文Hamon
- 互の目に、尖り刃交じり、足頻りに入り、湯走り・二十刃風頻りにかかり、小沸深くよくつき、金筋・砂流し細かく頻りにかかる。Gunome, Mixed Togariba, Ashi entered a lot, Yubashiri, Nijuba-shikirinikakari, Small-Nie entered deeply well, Kinsuji and Sunagashi entered sincerely and finely.
- 帽子Boushi
- 乱れ込んで小丸。Midarekonde-Komaru
- 茎Nakago
- 生ぶ、先入山形、鑢目鷹の羽、目釘孔二。Ubu, Sakiiriyamagata, Yasurime-Takanoha, Mekugiana are two(2)
- ハバキHabaki
- 銅一重Single copper
- 拵Sword mounitings
- 茶八重牡丹塗印籠刻鞘打刀拵 [江戸時代]
法量
長さ103.0cm 反り4.2cm
説明
鐔 銘 会津住 正阿弥作 鉄地車透、
縁頭 銘 大森英秀 花押 赤銅波濤図金象嵌。
目貫 赤銅地金色絵。 鯉口金具鐺 赤銅梅樹図金色絵。
Cha -Yae-Botan Nuri-Inrou Kizamisaya-UchikatanaKoshirae(Edo era)
(brown double peony Koshirae with lacquered seal casel and carved scabbard)
Length:103.0cm
Sori:4.2cm
Tsuba: Mei: Aidu jyu Syouami-saku
Tetsujikuruma-Sukashi
Fuchigashira: Mei: Ohmori-Hidetoshi kaou Syakudou Hatouzu Kinzougan
Menuki:Syakudouji Kiniroe
Koikuchikanagu Kojiri: Syakudou Baijyu(plum tree)-zu Kiniroe - 説明Drscription
- 兼元は、美濃三阿弥系の鍛冶で、古来名高いのは室町中期大永頃の二代兼元(通称孫六)で、末古刀の最上作として二代兼定と共に末関を牽引し、また、最上大業物としても知られるように切れ味に優れ、古来より武人に愛された。二代兼元以降代々孫六を通称としているが、「関の孫六三本杉」といわれるように兼元の代表的な刃文が三本杉乱れで、これは尖りごころの互の目が連なる様が三本杉のように見えたことからついた呼び名である。この刀は、兼の頭が離れているが、銘振り・茎仕立・互の目が不揃いとなる作域とも孫六兼元の典型的なもので、天文頃の晩年の作と思われ、常よりも小模様となる小乱れを焼き、足頻りにかかり、湯走り・二十刃かかり、金筋・砂流し頻りに掛るなど刃中が良く働き出来が良い。古研ぎ。登録証は採寸ミスのため二尺四寸一分になっております。Kanemoto is a blacksmith of the Mino Sanami lineage, and the one who has been famous since ancient times is the second Kanemoto (commonly known as Magoroku), who lived in the middle of the Muromachi period and was known as Magoroku. , Also known as the best Ohwazamono, it has excellent sharpness and has been loved by warriors since ancient times.
Since Kanemoto II, he has been known by the common name Magoroku for generations, but Kanemoto's representative Hamon is Sanbonsugi-Midare, as it is said to be ``Seki no Magoroku Sanbonsugi'', which looks like a pair of eyes with a pointed heart. It is the name given because it looked like Sanbonsugi.
Although the head of this sword is detached, it is typical of Magoroku Kane's head is separated from this sword, but the inscription, stem tailoring, and gunome are not evenly matched, which is typical of Magoroku Kanemoto's work, and is thought to have been made in his later years around the Tenmon era.
Small-Midare-yaki with a smaller pattern than usual, Ashi-shikirinikakaru, Yubashiri, Nijuba-kakari, Kinsuji and Sunagashi-shikirini-kakaru Works well inside the sword, Huru-togi, The registration card is 2 shaku 4 sun 1 min due to a measurement error.