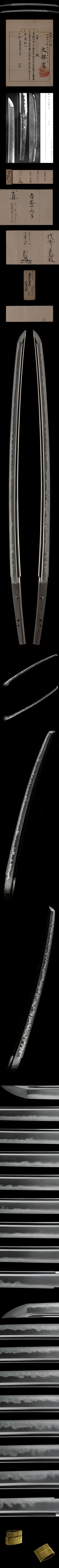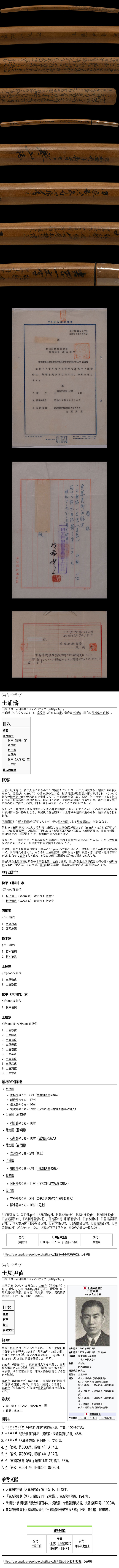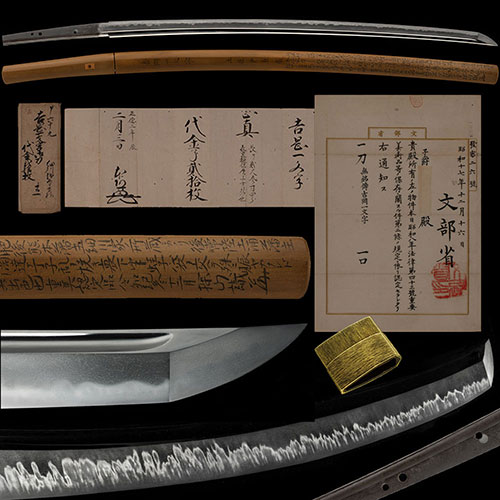
一文字 刀 Ichimonji Katana
No.978999刀 吉岡一文字 光忠折紙 伝来細川家-水戸徳川家-土屋家 鎬にまで掛る究極の華やかな丁子乱れ傑作 二尺三寸四分Yoshioka Ichimonji Mitsutada Origami Introducing the Hosokawa family-Mito Tokugawa family-Tsuchiya family The ultimate gorgeous Choji midare masterpiece that extends to Shinogi 70.9cm
ご成約Sold
- 極めKiwame
- 吉岡一文字Yoshioka Ichimonji
- 登録証Registration
- 東京都 Tokyo 昭和30年12月17日 12/17/30(Showa)
- 法量Size
-
刃長 70.9cm ( 二尺三寸四分) 反り 1.4cm
元幅 3.0cm 先幅 2.1cm 元重 0.60cm 鎬厚 0.69cm 先重 0.48cm 鋒長 3.8cm 茎長 19.4cm 重量 648gHachou 70.9cm ( 二尺三寸四分) Sori 1.4cm
Moto-Haba 3.0cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.60cm Shinogi-Thikess 0.69cm Saki-Kasane 0.48cm Kissaki-Chou 3.8cm Nakago-Chou 19.4cm Weight 648g - 国Country
- 備前Bizen
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り尋常、腰反りつき、中鋒。Shinogi-dukuri, Iorimune .Widely Mihaba, standard Sori, Koshizori-tsuki, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 板目肌つみ、杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、乱れ映り立つ。Itamehada-tsumi,Mixed Mokume-hada ,Jinie is finely and thick, Midare-utsuritatsu.
- 刃文Hamon
- 焼き幅大きな丁子に、重花風の丁子・袋丁子・蛙子調の丁子・互の目など交じり、足・葉よく入り、匂出来、小沸深くよくつき、金筋頻りにかかり、匂口明るい。Yakihaba big Choji,Juka-fu Choji, Fukuro Choji,Kawazuko Choji, Mixed Gunome, There are many Ashi and You. Nioi deki, Konie deeply and well. Kinsuji shikirinikakari, Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 乱れ込んで小丸。Midarekonde Komaru
- 茎Nakago
- 大磨上、先切、鑢目筋違。Ohsuriage, Sakikiri, Yasurimechigai
- ハバキHabaki
- 金着二重。Double gold.
- 彫物Carving
- 表裏に棒樋を掻き通す。On the front and back Bouhi Kakitoosu.
- 説明Drscription
- 鎌倉時代の備前物は、一文字と長船の両派に代表され、一文字派は以後南北長期にかけて福岡・吉岡・岩戸などの地に繁栄し、多くの良工が輩出した。この派が一文字と呼称される所以は、茎に「一」の字をきることに因るが、銘は「一」の字のみのものと、他に「一」の字の下にさらに個銘を加えるもの、また個銘だけのものもある。吉岡一文字派は、福岡一文字派に次いで鎌倉時代末期から南北朝期にかけて繁栄した。一派の代表工には助光・助吉・助茂・助次・助義などがいて「助」を通字としており、作風は、乱れの中に互の目が目立ってやや小出来となるものである。この刀は、身幅広く、腰反りつき、中鋒となる姿に、つんだ板目肌に、杢目交じり、乱れ映り立つ美しい地鉄に、鎬にまで掛かる焼き幅大きな丁子に、やや逆掛る重花風の丁子・袋丁子・蛙子調の丁子・互の目など交え華やかに乱れ、足・葉よく入り、金筋・砂流し頻りに掛かるなど刃中の働き豊かで、刃肉も残り頗る健全な傑作である。伝来は、正徳二年光忠折紙の包紙にあるように細川家より婚姻関係が深かった水戸徳川家に贈られ、水戸藩主徳川治保の三男が土浦藩9代藩主を継ぎ、徳川斉昭の子が土浦藩11代藩主を継いでいるのでどちらかの折に土屋家に移ったと思われる。白鞘には、昭和33年の寒山鞘書と昨年末に田野辺先生に書いていただいた鞘書がある。The Ichimonji faction prospered in places such as Fukuoka, Yoshioka, and Iwato over the Nanbokucho era, and many good workers were produced. The reason why this group is called Icimonji is that the letter "Ichi" is cut on the stem, but the inscription is only the letter "Ichi", and there are more pieces under the letter "Ichi". Some add Mei, others only Mei. The Yoshioka Ichimonji faction is second only to the Fukukoka Ichimonji faction.
It prospered from the end of the Kamakura era to the Nanbokucho era. Sukemitsu, Sukeyoshi, Sukeshige, Suketsugu, Sukeyoshi, etc. are the representative works of the group, and "Suke" is a common character, and the style is that Gunome is conspicuously small in the turbulence.
This sword looks like Widely Mihaba, Koshizori-tsuki, Chu-Kissaki, Itamehada-tsumi, Mixed Mokume-hada, Midareutsuritatsu beautiful Jigane, Yakihaba big Choji, Juka-fu Choji, Fukuro Choji, Kawazuko Choji, Mixed Gunome. , There are many Ashi and You. Nioi deki, Konie deeply and well. Kinsuji shikirinikakari, Nioikuchi is bright. The tradition was given to the Mito Tokugawa family, who had a deeper marital relationship than the Hosokawa family, as shown in the wrapping paper of Mitsutada Origami in the second year of Shoutoku. Since he succeeded the 11th feudal lord of the Tsuchiura feudal clan, it seems that he moved to the Tsuchiya family at some point. Shirasaya includes Kanzan Sayagaki in 1958 and Sayagaki written by Professor. Tanobe at the end of last year.