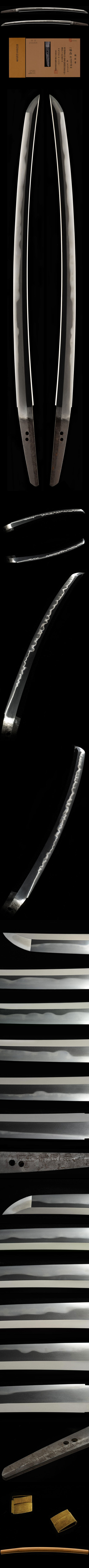国助 脇差Kunisuke Wakizashi
No.093110中河内 河内守国助 沸匂深く地刃冴える拳形丁子最高傑作 一尺九寸三分Nakakawachi Kawachinokami Kunisuke Deep NieNioi and clear Jiba Kobushigata-Chouji a masterpiece 58.4cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 河内守国助河内守国助 Kawachonokami Kunisuke
- 登録証Registration
- 千葉県 Chiba 53年2月24日 2/24/53
- 時代Period
- 江戸時代Edo era
- 法量Size
-
刃長 58.4cm ( 一尺九寸三分) 反り 1.7cm
元幅 3.2cm 先幅 2.2cm 元重 0.69cm 鎬厚 0.72cm 先重 0.51cm 鋒長 3.8cm 茎長 15.2cm 重量 598gHachou 58.4cm ( 一尺九寸三分) Sori 1.7cm
Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.69cm Shinogi-Thikess 0.72cm Saki-Kasane 0.51cm Kissaki-Chou 3.8cm Nakago-Chou 15.2cm Weight 598g - 国Country
- 摂津Settsu
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り尋常、元先の幅差つき、中鋒やや延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Standard Sori, With width difference of Motosaki, Chu-Kissaki slightly extended
- 鍛Kitae
- 小板目肌つみ、杢目交じり、地沸微塵につき、鉄明るい。Small-Itamehada-tsumi, Mixed Mokume, Jinie entered finely, Iron is bright.
- 刃文Hamon
- 焼き幅大きな互の目に、丁子交じり、足長くよく入り、葉入り、湯走り・飛焼きかかり、二十刃ごころとなり、小沸深くよくつき、荒沸を交え、砂流しかかり、匂口明るい。Yakihaba with Big-Gunome, Mixed Chouji, Long Ashi entered well, You entered, Yubashiri, Tobiyaki-kakari, Niju-bagokoro, Small-Nie entered deeply well, Mixed Ara-Nie and Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright.
- 帽子Boushi
- 直に小丸、やや深く返る。Suguni-Komaru,Go back a little deeper.
- 茎Nakago
- 生ぶ、先刃上り栗尻、鑢筋違、目釘孔二。Ubu, Sakiba-agari-Kurijiri, Yasuri-sujikai, Mekugiana are two(2)
- ハバキHabaki
- 金着二重。Double gold
- 説明Drscription
- 河内守国助の初代は、堀川国広の末弟子で、師没後、井上真改の父である親国貞と共に京から大坂に移住して大坂鍛冶の開拓者となった。国助家は元来勢州石堂家の出身で、石堂家本来の丁子を得意とし、同銘数代続く中で二代国助が中河内と称せられて最も上手である。この刀は、反り深くつく中河内晩年の作と思われ、小板目肌がつみ、地景細かく入る美しい鍛に、互の目乱れに、「拳形丁子」と称せられる独特の拳形の丁子を交え、足長く頻りに入り、沸よくつき、砂流しかかり、二十刃ごころになるなど焼き刃が変化に富み、中河内の特徴をよく表わしており、地刃が明るく冴えて出来がよい。最上砥ぎがかけられ、茎も鏨枕立ち、頗る健全な状態の二代国助の最高傑作である。The first generation of Kawachinokami Kunisuke was the youngest disciple of Kunihiro Horikawa, and after his master's death, he moved from Kyoto to Osaka with OyaKunisada, the father of Shinkai Inoue, and became a pioneer of blacksmithing in Osaka. The Kunisuke family originally came from the Ishido family in Seshu, and they specialize in cloves, which is the original clove of the Ishido family.
This sword is deeply Sori is thought to have been made in the
late years of Nakakawachi. Small-Itamehada,Chikei entered finely with Beautiful Kitae, Gunome-Midare, With a unique fist-shaped Chouji called "Kobushigata-Chouji", Ashi entered long, Nie entered well, Sunagashi-kakari, Nijuba-Gokoro, Yakiba is rich in variety. It expresses the characteristics of Nakakawachi well, It works good and Jiba is bright and clear,It is the masterpiece of Kunisuke II, which has been polished to the highest quality, the stems stand upright, and is in an extremely Kenzen state.