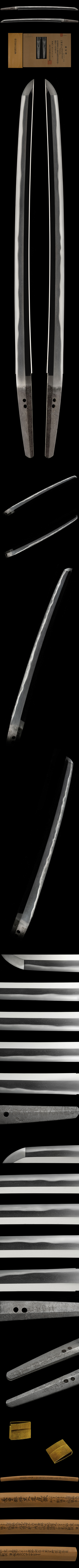虎徹 脇差Kotetsu Wakizashi
No.541764長曽祢虎徹入道興里 寛文四年六月吉祥日 金筋砂流し頻りに掛り匂深く地刃明るく冴える傑作 一尺六寸八分Nagasone Kotetsu Nyudo Okisato Kanbun 4th June auspicious day Kinsuji, Sunagashi-shikirinikakaru Deep Nioi and Jiba is bright and clear a masterpiece 50.8cm
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 長曽祢虎徹入道興里 長曽祢虎徹入道興里 Nagasone Kotetsu Nyudo Okisato
- 裏銘Ura-mei
- 寛文四年六月吉祥日 寛文四年六月吉祥日 Kanbun 4th June auspicious day
- 時代Period
- 江戸時代前期Early Edo period
- 法量Size
-
刃長 50.8cm ( 一尺六寸八分) 反り 0.5cm
元幅 2.9cm 先幅 2.0cm 元重 0.53cm 鎬厚 0.59cm 先重 0.42cm 鋒長 2.9cm 茎長 14.7cm 重量 428gHachou 50.8cm ( 一尺六寸八分) Sori 0.5cm
Moto-Haba 2.9cm Saki-Haba 2.0cm Moto-Kasane 0.53cm Shinogi-Thikess 0.59cm Saki-Kasane 0.42cm Kissaki-Chou 2.9cm Nakago-Chou 14.7cm Weight 428g - 国Country
- 武蔵Musashi
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反りやや浅く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, Slightly shallow Sori, Chu-Kissaki.
- 鍛Kitae
- 小板目肌に、板目肌・流れ肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景入り、鉄明るく冴える。Small-Itamehada, Itamehada and mixed Nagarehada, Jinie entered fine and thick, Chikei entered well , Iron is bright and clear.
- 刃文Hamon
- のたれに、互の目交じり、湯走り二十刃掛り、足・葉よく入り、沸よくつき、金筋・沸筋・砂流し頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。Notare, Mixed Gunome, Yubashiri, Nijuuba-kakari, There are many Ashi and You, Nie entered well, Kinsuji, Niesuji, Sunagashi-shikirinikakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.
- 帽子Boushi
- 直に小丸、やや深く返る。Suguni-komaru,Go back a little deeper.
- 茎Nakago
- 生ぶ、先栗尻、鑢目筋違、目釘孔二。Ubu, Sakikurijiri, Yasurimesujikai, Mekugiana are 2.
- ハバキHabaki
- 金着二重。Double gold
- 説明Drscription
- 長曽祢虎徹は、江州彦根の長曽祢に生まれ、越前福井で甲冑師となり、承応頃(1652年)、五十歳の時に江戸に移り刀鍛冶に転じた。通称を三之丞と称し、入道して「こてつ入道」といい、初めは「古鉄」の字を用い、後に「虎徹」(はねとら銘)の文字を、さらに寛文四年からは「乕徹」(はことら銘)を使用している。年紀作は明暦二年から、延宝五年に渡り、延宝六年七十余歳で上野池之端に没する。当時その斬新な作風は一世を風靡し、新刀随一の巨匠として技量は高く評価されている。この刀は、寛文四年六月の年紀が入るはこ虎銘に変わる直前の作で、反りの浅い寛文新刀の姿を呈し、地沸微塵に厚く付き、地景入る冴えた地鉄に、互の目が連れた所謂数珠刃と呼称される刃を交え、さらに瓢箪刃も交え変化があり、湯走り・二十刃掛り、足・葉よく入り、沸よく付き、金筋・沸筋・砂流し頻りに掛るなど刃中よく働き、覇気溢れ、匂深く、匂口明るく冴え渡る傑作である。Nagasone Kotetsu was born in Nagasone Kotetsu in Hikone, Echizen, and became an armorer in Echizen Fukui. He commonly known as Sannosuke, and when he entered the road, he called it "Kotetsu Irido". At first, he used the character "Kotetsu", and later the character "Toru" (Hanetora inscription), and from the 4th year of Kanbun. "Tetsu" is used. His chronological work spans the 5th year of Enpo from the 2nd year of the Meireki era, and died in Ikenohata Ueno at the age of 70 years in the 6th year of Enpo. At that time, his novel style was predominant in the world, and his skill as the best master of new swords is highly evaluated.This sword was made just before it changed to Hakotora, which has the date of June 4th year of Kanbun, and shows the appearance of a Kanbun new sword with a shallow Sori. Jinie entered fine and thick, Chikei entered clear Jigane, Crossing the blade called the so-called Juzuba brought by Gunome.
In addition , The In addition, the Hyotan blade also has a change,Yubashiri, Nijuba-kakari, There are many Ashi and You, Nie entered well. Kinsuji, Niesuji, Sunagashi-shikirinikakaru.Hachu good work, overflowing with ambition, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear a masterpiece.