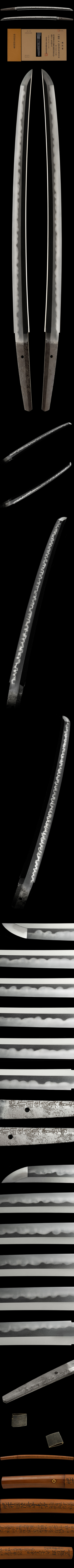三代 忠吉 Tadayoshi III
No.886647三代 肥前国住陸奥守忠吉 重要レベル 華やかに乱れ匂口明るく冴える屈指ノ優品也 深山鞘書3rd Hizennokuni jyu Mutsunokami Tadayoshi Juyo level Gorgeously Midare Nioikuchi is bright and clear, one of the best good works Miyama Sayagaki
ご成約Sold
- 銘表Mei-Omote
- 肥前国住陸奥守忠吉 肥前国住陸奥守忠吉 Hizennokuni jyu Mutsunokami Tadayoshi
- 法量Size
-
刃長 54.0cm (一尺七寸八分強) 反り 0.8cm
元幅 3.2cm 先幅 2.2cm 元重 0.70cm 鎬厚 0.77cm 先重 0.51cm 鋒長 3.7cm 茎長 16.3cm 重量 630gHachou 54.0cm (一尺七寸八分強) Sori 0.8cm
Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.70cm Shinogi-Thikess 0.77cm Saki-Kasane 0.51cm Kissaki-Chou 3.7cm Nakago-Chou 16.3cm Weight 630g - 国Country
- 肥前Hizen
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り尋常、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Standard Sori, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 小板目肌つみ、地沸微塵に厚くつき、地景細かく入り、鉄冴える。Small-Itamehada-tsumi, Jinie entered fine and thick, Chikei finely entered, Iron is clear.
- 刃文Hamon
- 中直刃、小足入り、小沸深くよくつき、匂口明るい。帽子、直ぐに小丸。Chu-suguha, Small-Ashi entered, Deep small Nie entered often, Nioikuchi is bright. Boushi Suguni-komaru.
- 帽子Boushi
- 直ぐに小丸。Suguni-komaru
- 茎Nakago
- 生ぶ、先入山形、鑢目勝手上り、目釘孔一。Ubu, Sakiiri-yamagata, Yasurimekatteagari, Mekugiana is 1.
- ハバキHabaki
- 銀着一重。Single silver.
- 説明Drscription
- 陸奥守忠吉は、名を橋本新三郎といい、寛永十四年(1637年)に近江大掾忠広の長男として生まれ、万治三年(1660年)十月に陸奥大掾を受領、翌年の寛文元年(1661年)八月に陸奥守に転任、父近江大掾忠広より7年早く、貞享三年(1686年)一月に50歳で没したため、ほとんど父の代作に従事していたものと考えられる。したがって、長命であった祖父や父と比べて三代忠吉自身の作刀は少ないが、出来の優れた作刀が多く、地鉄の精緻や地刃の冴えにおいては初代を凌駕するといわれており、価格に於いても、初代忠吉よりも高く評価されている。この刀は、身幅3.2cmと広く、重ね厚く、反りやや浅い寛文新刀の豪壮な姿で、小杢目肌がよく錬れて、地沸微塵に厚くつき、地景細かく入る所謂小糠肌と呼称される究極の冴えた地鉄に、焼き幅大きな互の目に、丁子刃交じり、足・葉よく入り、小沸深くよくつき、金筋幾重にも頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴え渡る。田野辺先生も乱刃屈指ノ優品と記している通り三代陸奥の最高傑作である。Mutsunokami Tadayoshi, whose name is Shinsaburo Hashimoto, was born in 1637 as the eldest son of Oumidaijou Tadahiro, and received Mutsudaijou in October 1660.He was transferred to Mutsunokami in August of the first year of Kanbun (1661) the following year, and died at the age of 50 in January of the third year of Jokyo (1686), seven years earlier than his father Oumidaijou Tadahiro, so he was mostly engaged in his father's work. It is considered to be.
This sword has a wide width of 3.2 cm Mihaba,Thick Kasane, and is a magnificent figure of Kasane thick, Sori, a slightly shallow Kanbun new sword.With the magnificent appearance of Kanbun new sword, Small Mokumehada Nerete, Jinie entered fine and thick, Chikei finely entered, the ultimate clear Jitetsu called Konuka-hada, Yakihaba big Gunome, Chouji-ba mixed, Ashi and You entered well, Konie deeply and well-attached, Kinsuji many times Shikirini-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.
As Professor. Tanobe also wrote that It is the best masterpiece of Mutsu III, as Dr. Tanobe also describes it as one of the best products of Midare-ba.