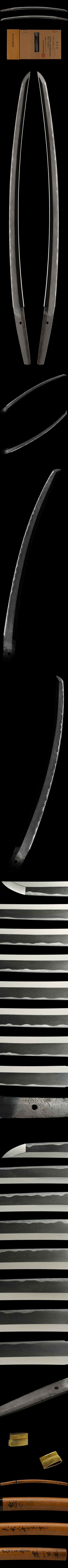兼元(孫六)刀Kanemoto(Magoroku) Katana
No.539020刀 兼元(孫六)最上作 最上大業物 映り立ち金筋頻りに掛る三本杉典型作名品 時代拵付 二尺一寸五分五厘Kanemoto (Magoroku) Top work Saijo Ohwazamono Utsuritachi Kinsuji Frequently hung Sanbonsugi (3 Cedar) Typical masterpiece with Jidai Koshirae 65.0cm
ご成約Sold
関連商品
- 極めKiwame
- 兼元(孫六)Kanemoto(Magoroku)
- 登録証Registration
- 三重県 Mie 昭和26年3月31日 3/31/26(Showa)
- 法量Size
-
刃長 65.0cm (二尺一寸五分五厘) 反り 2.3cm
元幅 3.2cm 先幅 1.9cm 元重 0.50cm 鎬厚 0.62cm 先重 0.35cm 鋒長 3.4cm 茎長 16.0cm 重量 543gHachou 65.0cm (二尺一寸五分五厘) Sori 2.3cm
Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 1.9cm Moto-Kasane 0.50cm Shinogi-Thikess 0.62cm Saki-Kasane 0.35cm Kissaki-Chou 3.4cm Nakago-Chou 16.0cm Weight 543g - 国Country
- 美濃Mino
- 姿Shape
- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、中鋒。Shinogi-dukuri,Iorimune, Widely Mihaba ,Deep Sori, Chu-Kissaki
- 鍛Kitae
- 鍛は、板目肌に、杢目肌・ 流れ肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景入り、映り立つ。Kitae is Itamehada,Mixed Mokumehada, Nagarehada, jinie Fine and thick, Chikei is reflected.
- 刃文Hamon
- 互の目が連れ、尖り刃交じり、湯走り掛り、足よく入り、小沸つき、金筋・砂流し掛り、匂口明るく冴える。帽子、乱れ込んで先掃きかけて返る。Gunome-tsure, Mixed Togariba, Yubashiri-kakari, There are many Ashi with Konie, Kinsuji, Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright and clear.
- 帽子Boushi
- 乱れ込んで先掃きかけて返る。Midarekonde Sakihakikakete-kaeru
- 茎Nakago
- 茎は生ぶ、先入山形、鑢目鷹ノ羽、目釘孔一。Ubu Nakago, Sakiiriyamagata, Yasurime takanoha, Mekugiana is 1.
- ハバキHabaki
- 金着二重。Double gold.
- 拵Sword mounitings
- 黒蝋色塗鞘打刀拵
法量
長さ101.4cm 反り5.0cm
説明
鐔 銘 奈良 永春 花押 赤銅石目地柳に鷺図金色絵、 縁頭 赤銅魚子地扇に葵図金色絵。 目貫 金無垢這竜図。 Black wax-colored Uchigatana-Koshirae
Size
Length; 101.4cm
Sori; 5.0cm
Description
Tsuba; Mei Nara Nagaharu, Kaou Shakudo stone joint Yanagi with a golden picture of Sagi,
Fuchigashira:Syakudounanakoji Aoi crest Kiniroe (Aoi figure golden painting on a red bronze fan)
Menuki:Kinmuku Hairyu-zu(Innocent gold dragon figure.) - 説明Drscription
- 兼元は、美濃三阿弥系の鍛冶で、古来名高いのは室町中期大永(1521年~)頃の二代兼元(通称孫六)で、末古刀の最上作として二代兼定と共に末関を牽引し、また、最上大業物としても知られるように切れ味に優れ、古来より武人に愛された。二代兼元以降代々孫六を通称としているが、「関の孫六三本杉」といわれるように兼元の代表的な刃文が三本杉乱れで、これは尖りごころの互の目が連なる様が三本杉のように見えたことからついた呼び名である。この刀は、身幅広く、反り深く、中鋒、茎が短い片手打の姿で、板目に杢目交じり、刃寄り流れ肌交え、地沸微塵に厚くつき、地景入り、乱れ映り立つ地鉄に、不揃いに互の目が連れる孫六の三本杉の作風となり、小沸付き、金筋・砂流し掛るなど刃中の働き盛んで、匂口明るく冴える二代兼元の名品である。Kanemoto is Kaji of the Mino Sanami system, and the old famous one is Kanemoto (commonly known as Magoroku), the second generation around Taiei (1521-) in the middle of the Muromachi period. , Saijo-Ohwazamono, also known as Saijo-Ohwazamono, has excellent sharpness and has been loved by warriors since ancient times. Magoroku has been known as Magoroku for generations since the second generation Kanemoto, but as it is called "Sekino Magoroku Sanbonsugi (3 Cedar)", Kanemoto's representative sword is Sanbonsugi Midare, which is Sanbonsugi (3 Cedar) with Gunome of Togarigokoro. ) Is the name given to it because it looked like.
This sword is Mihaba wide, Sori deep, Chu-Kissaki, Nakago short Katate-uchi, Itame mixed with Mokume, Hayorinagare Hadamajie, Jinie atacched finely, Chikei entered, Jigane raggedly accompanied by Gunome. It is the style of Sanbonsugi (3 Cedar) of Magoroku, and it is a masterpiece of the second generation Kanemoto who is bright and clear with Konie, Kinsuji, Sunagashi, etc.